
こんにちは、鮨ブロガーの、すしログ(@sushilog01)です。
本記事は「旬の魚」をご紹介する「旬魚の世界シリーズ」です。
当シリーズでは、旬の魚の魅力を鮨ブロガーならではの目線で解説していきます。
今回は「シマアジ(縞鯵)」についてご紹介します。
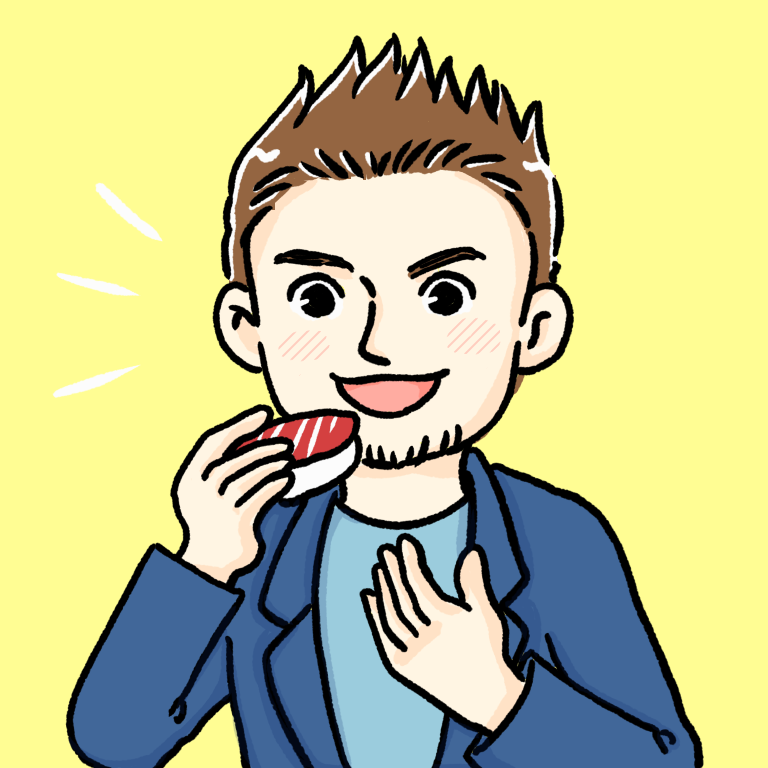 すしログ
すしログ
楽しんで頂ければ幸いです。
▼シリーズのまとめ記事はこちらです
シマアジ(縞鯵)の基本情報と旬は?

標準和名:シマアジ(縞鯵・島鯵)
通称・別称:特大サイズは東京でオオカミ、和歌山でソイと呼ばれる
英語名:White trevally, Striped jack
旬:6月~8月
シマアジ(縞鯵)についてのすしログ的コメント

シマアジは「アジ科シマアジ属」となり、マアジ=「アジ科マアジ属」とは異なります。
「シマ」が付くと何となく可愛い響きになりますが、実際はマアジよりも大型のタフな魚。
大きいものは100~120cmほどにもなります。
名前に「シマ」が付く理由については、体側に黄色い横「縞」があるから、伊豆七「島」が主産地だからなど諸説あります。
市場に出回る99%以上が養殖モノであるため、天然モノは高級魚です。
シマアジ、カンパチ、ヒラマサ、ワラサ(稚鰤)は全てアジ科で近しい魅力のある魚たちですが、シマアジが抜きん出て高評価を得ています。
鮨店で気取らない職人さんが「シマアジです」とさらっと出されて、「ああ、アジ系ね」などと流される方がいらっしゃったら、それは大変勿体無い!
マアジとは異なる味わいがあり、夏を代表する脂が乗った青魚なので、じっくり吟味するとありがたみがアップして結果的に味わいがアップします。
食って、そう言うものですよね。
天然モノと養殖モノの味の違いについては、かなり異なります。
養殖モノは脂が乗っていて、これはこれで美味しいと思います。
鮨店で出てくるクオリティであれば、養殖のハマチのような媚びるような脂ではないので、酢飯との相性も良く、夏のタネとしては力強い味わいを楽しませてくれます。
しかし、天然モノは脂だけでなく香りと歯ごたえが特徴的です。
引き締まった身は雄々しい磯の香りを発し、サッパリなのにコクが強い…
一度頂けば鮮烈な印象を覚えます。
特に香りの点において。
そして、「サッパリなのにコクが強い」と言う味の理由は、シマアジが「ヒラアジ類」と呼ばれる仲間に属するためです。
「ヒラアジ類」は外見こそ青魚ですが、白身魚と青魚の中間的な味わいを持ちます。
よって、青魚にしては少しサッパリした魚味があるのだと思います。
鮨店での分類も光り物ではなく、白身魚。
ゼイゴは正しくアジらしく、見た感じは完全に青魚なんですけどね。
なお、「ヒラアジ類」で味が良い高級魚扱いの魚としては、他にカイワリも有名です。
有名と言ってもシマアジに比べると全然ですが、魚味は流石高評価なだけある魚です。
シマアジと比較すると、繊維質がみっちりしていて、酸味があり、よりサッパリした印象を覚える事が多いです。
シマアジが100cmほどになるのに対して、カイワリは最大で40㎝ほどなので、魚体の違い(エサの質と量の違い)が味に影響しているのではないかと思います。
シマアジ(縞鯵)の鮨における仕事(調理法)

シマアジ(縞鯵)の鮨における仕事(調理法)は以下の通りです。
- 寝かせる/熟成
- 軽い漬け
味にパワーのある魚なので、熟成に向いています。
また、天然モノは上述の通り強い香りがあるので、熟成を掛けても持ち味を失いにくい特性があります。
最低2日くらい(人によっては3〜4日以上とも)寝かせて、そこから旨味を引き出した方が天然モノのシマアジの魅力があると感じます。
ただ、個人的に香りは勿論、食感も残す事が必須だと思います。
折角貴重な天然モノを用いながら単なる旨味の集合体にしてしまうのは勿体ないです。
そして、脂も旨味も強いと言う事は、軽い漬けの仕事がピッタリです。
軽く漬けにすると身がねっちりして味わいが強くなるので、シャリの酸味と乳化した時の印象を強めます。
このあたりの仕事との相性の良さは、冬のブリ、夏のシマアジと言うイメージです。
食べる時はここに注目!

鮨でシマアジを食べる時に注目するポイントはこちら!
- 脂
- 香り
「脂」と書くと身も蓋もないのですが、同時に香りも楽しむとシマアジの良さを実感できるかと思います。
天然モノは本当に香りが良いので。
雄々しい磯の香りは脂や旨味の余韻とともにしばらく残り続けます。
目を瞑れば、伊豆の海流を威勢よく泳ぐシマアジの姿が浮かぶ程です(笑)
夏場はマアジも美味しいですが、完全に異なる魅力がありますね。

掲載した写真のお店
北海道のお店ばかりですみません(笑)
ちなみに、文中に登場したカイワリを出されるお店は東京だと2軒。
銀座の鮨処やまださん
渋谷の花おかさん
他は小田原、熱海の酒場で頂いた事がある程度です。
▼シリーズのまとめ記事はこちらです
鮨と魚をこよなく愛する、鮨ブロガーのすしログ(@sushilog01)でした。
本記事のリンクには広告がふくまれています。





